
通訳の基礎知識
今回は通訳の種類と特徴をまとめてみました。
通訳の基礎知識ですのでしっかり理解しておきましょう。
通訳は3種類あります
通訳の仕方によってそれぞれに最適な場所や必要な人数が違います。
どの形式がもっとも適しているのかを事前に検討しておきましょう。
ほぼ同時に発言内容を通訳する「同時通訳」
ほぼ同時に発言内容を通訳する方法。
通訳者が発言者の声を聞き、その内容を即座に翻訳して話すというものです。
通訳者は話を聞き、翻訳して、話して伝える、ということを瞬時にしなければならないためとても集中力が必要です。

同時通訳が使われる場面
大規模な会議や株主総会、学会、講演会、パネルディスカッション、シンポジウムなどで取り入れられています。
大人数で話し合うときや時間が長いディスカッションのときには同時通訳が適しています。
同時通訳の人数
同時通訳は非常に集中力が必要であり、長時間を1人でこなすのは困難。15分〜20分ごとに交代する必要があります。
半日の会議の場合は2名以上、1日にわたる会議は3名〜4名以上の人数が必要です。
数文まとめて通訳を行う「逐次通訳」
発言者が数文を話したあとに一旦話すことをやめて、その間に通訳者が訳す方法。
発言者が数文話し、そのあとに通訳者が通訳を行う、ということを繰り返していきます。
同時通訳とは違い、数文をまとめて通訳できるので、ゆっくりと落ち着いて通訳を聞くことができます。
同時通訳はほぼタイムラグがないのに対して、逐次通訳では普通に話す倍の時間がかかります。そのため長時間の会議などには不向きな方法です。

逐次通訳が使われる場面
ゆっくりと慎重に進めたい場合に利用されます。小人数での対談や商談に適しています。
逐次通訳の人数
同時通訳よりも進行するペースは遅いため、ある程度の時間を一人で担うことができます。
目安として、3時間以上は2名~3名、3時間未満は1名で対応可能です。
テンポよく会話を進められる「ウィスパリング」
通訳者が聞き手の近くにいて、通訳してすぐに伝える方法。囁くように伝えるところから「ウィスパリング」と呼ばれています。
会話の流れを止めることなくテンポよく進行できる方法です。

ウィスパリングが使われる場面
少人数での対談、商談や会議に適しています。
ウィスパリングの人数
同時通訳と同じく集中力が必要ですので、半日で2名〜3名、1日は4名程度の通訳者が必要になります。
通訳のセオリーを知ると通訳を取り入れた配信の仕方が見えてきます。
一緒に学んでイベントを成功させましょう。
次回はZoomの同時通訳機能「言語通訳」について解説します。
あわせて読みたい
-
前の記事

オンライン配信でも通訳を入れたい! と思ったときに最初に読むコラム 1
-
次の記事






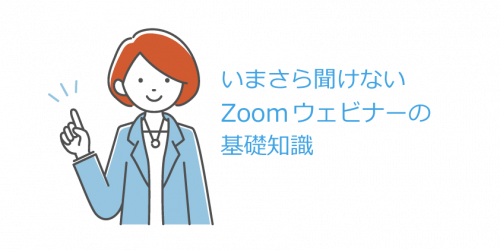






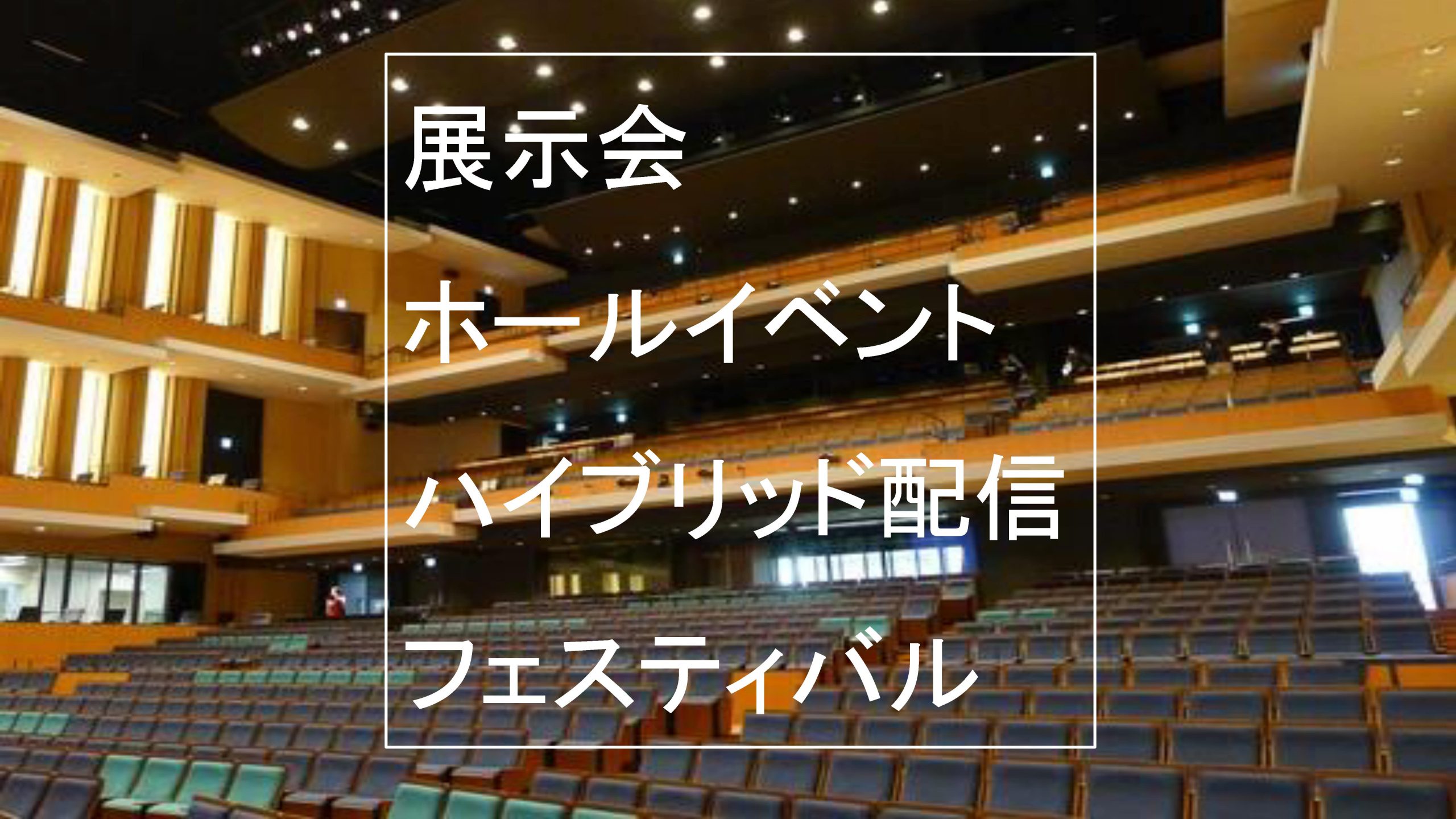



 03-6758-1037
03-6758-1037