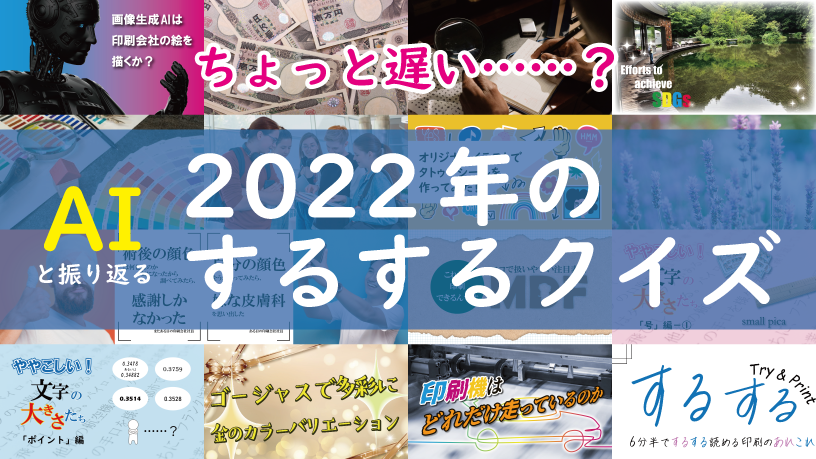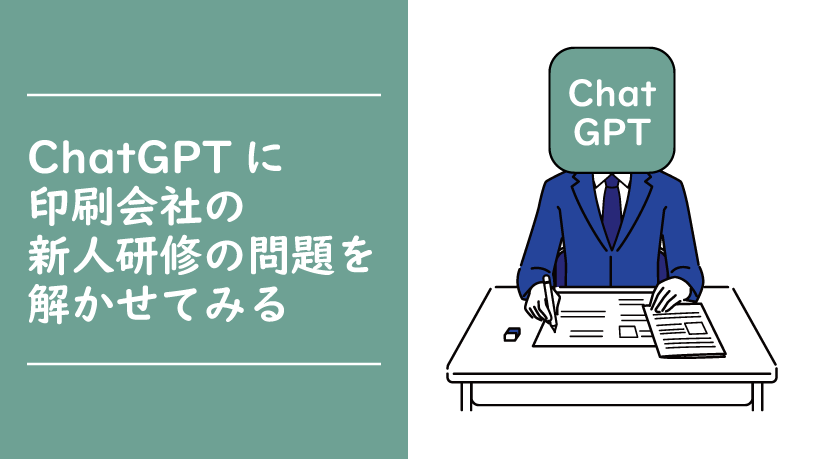画像生成AIは印刷会社の絵を描くか? 後編

前編に引き続き、お絵描きAIに“印刷会社”の絵をお願いしていきます。前回の教訓を活かしつつ、今回こそAIの引き出しを存分に発揮してもらいましょう!
お題その2:「印刷会社の営業マン」
今回のお題は「印刷会社の営業マン」です。印刷から製本まで幅広い知識を持ち、お客様のご要望に応えつつ最適な仕様をご提案する――印刷会社の顔ともいえる存在ですから、きっちり描いていただきたいところですね! 営業マンならサンプルとなる画像も大量にあるでしょうし、印刷機ほど細部の精度が重要になるわけでもないので、よりスムーズに描いてくれそうです。
まずキーワードを英語に直します。印刷会社の営業マン→printing company salespersonとなります。それでは早速描いてもらいましょう!
↓
↓
↓




うーむ、別におかしくはないのですが、どちらかというと機械のメンテナンスに来てくれたメーカーの方ではないでしょうか(いつも助かっています!)? 「印刷会社に来た」ではなく「印刷会社から来た」ということをはっきりさせるため、キーワードをsalesperson from printing companyに変更してみましょう。
↓
↓
↓




あまり変化は見られませんね。それどころかなぜかセピアの画像が出てくるようになりました。
その後もsalesperson と printing companyのさまざまな組み合わせを試したのですが、ピンとくるものは出てこないまま。そんななか、一つの疑問が沸き起こりました。
印刷会社=printing companyとはいえない?
ここまで「印刷会社」の英訳をGoogle翻訳にかけてprinting companyとしていましたが、そもそもこの表現は適切なのでしょうか? というのも、英語圏で権威のあるオックスフォードやケンブリッジ、ロングマンの辞書にはprinting companyという語は載っていないのです。もちろんGoogleでprinting companyと検索すれば英語圏の印刷会社がヒットするので、ある程度通じる語ではあるようなのですが、正式な呼称とはいえないようです。
では「印刷業を営む会社」はなんというのか? 上の3つの辞書に共通して掲載されていたのはprinterという語でした。printerはそれぞれの辞書で以下のように説明されています。
(Oxford Learner’s Dictionaries)
1. a machine for printing text on paper, especially one connected to a computer
2. a person or a company whose job is printing books, etc.
(Cambridge Dictionary)
1. a machine that is connected to a computer and makes writing or images on paper
2. a person or company that prints books, newspapers, magazines, etc.
(Longman Business English Dictionary)
1. a machine which is connected to a computer and can make a printed record of computer information
2. a company which prints books, newspapers etc, or the person running such a company
どの辞書でも二通りの説明がありますが、一つ目はオフィスなどにあるいわゆる「プリンター」のこと。二つ目は「印刷業に従事する会社・人」といったニュアンスで、今回でいう印刷会社にはこちらが当てはまります。
ただ、人間/AIに限らず”printer”と聞いたときにはじめに思い浮かぶのはまちがいなく一つ目の「プリンター」でしょう。念のためStable Diffusionにprinterと指示を出してみましたが、やはり機械のほうの絵しか描いてくれませんでした。
本題に戻りましょう
英語で運用しているシステムである以上、画像生成が英語のボキャブラリーに縛られてくるのは想定していましたが、あろうことか「印刷会社」にあたる語の選定に罠があるとは……。「印刷会社」という語を使わずに「印刷会社の営業マン」をAIに表現させる、というミッションが発生してしまいました。
そうなると……salesperson with 〇〇のような形式で、印刷会社の営業を想起させるアイテムを〇〇に押し込むという方法が現実的なのかもしれません。もちろん最初に思い浮かんでくるのは印刷機ですが、前回のチャレンジの顛末を踏まえると避けたほうがよさそう。他のアイテムを考えてみましょう。
印刷営業必須アイテムその1
印刷会社の営業特有のアイテムといえば……ルーペはどうでしょうか?
印刷物の絵柄はごく小さなインクの点:網点によってできています。この網点の付き具合を確認するためにルーペを使って絵柄をのぞき込むことがあります。特に印刷が高精細になればなるほど網点は小さくなるので、仕上がりを確認するためにはルーペが必須。印刷物の品質をチェックする場面では必ずと言っていいほどお世話になるアイテムです。

こちらのアイテムは英語ではprinting loupe、printer’s loupe、あるいはprinter’s magnifying glassなどと呼ばれている様子。どれも一単語にまとまっていないのが不安要素ですが、全部試してみましょう!
salesperson with printing loupe
↓
↓
↓




salesperson with printer’s loupe
↓
↓
↓




salesperson with printer’s magnifying glass
↓
↓
↓




大失敗ですね! 印刷会社らしさがかけらもありません。ところどころ宴会グッズ風になっているのは季節柄でしょうか。
冗談はさておき、取り上げたアイテムがちょっとマニアックすぎたようです。あとでsalespersonを除いてprinting loupe / printer’s loupe / printer’s magnifying glassのみで生成しても正確な画像は全く出てこなかったので、キーワードを再考します。
印刷営業必須アイテムその2
他に印刷会社の営業マンと縁のあるアイテムは……カラーガイドの出番でしょうか?


カラーガイドとは色見本帳とも呼ばれ、印刷や出版・デザインなどの業界ではよく知られたアイテムです。印刷において色とはCMYKの4色を重ね合わせて再現するのが基本ですが、なかには4色の重ねでは再現が難しく、専用のインキでないと出せない色:特色というものもあります。カラーガイドはこの特色に番号をつけ、一覧としてまとめたものをいいます。
色の印象は見る環境によって左右される部分が大きく、同じ色でも照明やモニターの設定次第で全く違う色に見えることがあります。だからこそ、色のイメージを共有するためにはまずお互いに共通の基準を持たなければなりません。そんなときに活躍するのがカラーガイドです。この色はこの番号、あの色はあの番号と決まっており、色味の伝達において共通言語の役割を果たしてくれるのです。
それでは、カラーガイドを持った営業マン:salesperson with color guideでチャレンジ!
↓
↓
↓




なんだか妙に楽しそうな画像がたくさん出てきましたが、カラーガイドはこんな使い方をするアイテムではない気がします。Stable Diffusionのボキャブラリーにカラーガイドは確かに存在するようですが、より実情に即した画像が欲しいところです。
日本の印刷会社ではカラーガイドといえば国産のDICとアメリカ発のPANTONEの2つのブランドを併用しているところが多いのですが、英語圏ならばPANTONEが一般的なはず。ということは、Stable Diffusionが学習したカラーガイドの画像もPANTONEのものである可能性が高いと思われます。思い切ってsalesperson with pantone color guideではどうでしょうか?
↓
↓
↓




突如今日一のリアリティに到達しました。お客様のご要望を踏まえてカラーガイドを確認していく、まさにその場面が描かれています。印刷会社の営業マンとして欠かせないワンシーンができあがりました。
固有名詞が入ると画像生成にノイズが発生しにくくなり、結果として精度が向上したのだと思われます。さすがはPANTONE。ちなみにカタカナで「パントーン」と表記・発音されるケースをよく見聞きしますが、日本の代理店の表記によると「パントン」が正しいようです。
おそらくまだまだやりようによっては精度を上げていける可能性もありますが、今回はここまで。みなさんも何か思いついたらぜひチャレンジしてみてください!
まとめ
Stable Diffusionが描く“印刷”は惜しいところまでは行っているのですが、どれも詰めが甘い。あまり重箱の隅をつついてもしょうがないのですが、実際に印刷にかかわる側からみるとまだまだ改善の余地があります。
ところで、AIが絵を描く材料にしているのは巷にあふれる画像と単語の組み合わせ。つまり、AIの印刷への認知度は一般の方々のそれからあまり遠くないということでもあります。そうなると、AIに正確な絵を描いてもらうためには印刷や印刷会社がそれこそ誰にでもくっきりと思い浮かぶほどの存在にならなければならないのかもしれません。
するするが盛り上がればStable Diffusionの絵のクオリティが上がる……のかはわかりませんが、引き続きこのサイトが多くの人に“印刷”を知ってもらえるきっかけとなるよう、今後も更新に励んでいきます!
参考
Stable Diffusion デモ版
https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion
“printer”
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/printer?q=printer(Oxford Learner’s Dictionaries)
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english-japanese/printer(Cambridge Dictionary)
https://www.ldoceonline.com/jp/dictionary/printer(Longman Business English Dictionary)